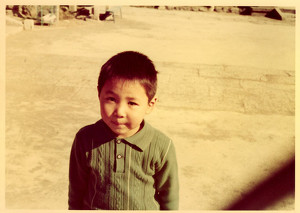論文が、International Journal of Informatics Society (IJIS) Vol. 14, No 1 にて公開されました。発行は2022年6月となっています。博士取得のキーとなった論文の一つです。
タイトルは、
Continual Lengthening of Titles: Implications for Deep Learning Named Entity Recognition
日本語では「長くなり続ける題名たち:深層学習固有表現抽出に対する示唆」です。
この論文では音声対話インターフェースを作成する際の語彙情報について議論しています。語彙情報の重要なものの一つに固有名詞があり、固有名詞のうちとくに小説、映画、漫画、アニメなどの「題名」に注目しています。これらの題名は年々長くなっています。過去のデータで学習した機械学習モデルでは、新しく発生した、より長い題名の検出に問題が発生することと、それに対して、検出時の特徴量に語彙情報を付加すると問題が軽減できる、という仮説のもと、データを整備し実験を行い、改善できることを示したものとなっています。
ご興味のある方はダウンロードしてご覧ください。